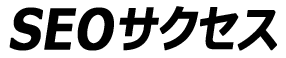LLMO対策とは?SEOとの関係性や基本から対策方法を解説
インターネットでの情報収集のあり方は、いま大きな変化の波に直面しています。
従来はGoogleやYahoo!などの検索エンジンにキーワードを入力し、検索結果から必要な情報を得るのが一般的でした。
しかし近年は、ChatGPTやGemini、Perplexityといった生成AIに自然な言葉で質問し、その場で答えを得るユーザーが急増しています。
こうした行動変容によって、「検索結果に表示される」ことだけでは不十分になりつつあり、「AIの回答に引用されるかどうか」が新たな競争軸として浮上してきました。
この新しい時代に対応するための考え方がLLMO(Large Language Model Optimization:大規模言語モデル最適化)です。
LLMOは、生成AIに自社の情報が正しく認識・参照されるように最適化を行うアプローチであり、従来のSEOとは異なる視点からWebコンテンツの価値を高める取り組みといえます。
本記事では、LLMOの基本概念からAIOやSEOとの違い、具体的な実践方法、さらに生成AI時代におけるマーケティングの構造変化について詳しく解説していきます。
LLMOとは?
LLMO(Large Language Model Optimization:大規模言語モデル最適化)とは、ChatGPTやGemini、Perplexity、GoogleのAI Overviewsなどの生成AIが回答を作成する際に、自社のWebコンテンツが正しく認識され、引用・参照されやすくなるように最適化する手法を指します。
従来のSEOが検索エンジンの検索結果で上位表示されることを目的としていたのに対し、LLMOは「AIが返す答えに自社の情報を含ませる」ことを目標とする、新しい時代の最適化アプローチです。
つまり、SEOが「検索結果ページでの露出」を重視するのに対し、LLMOは「AIの回答そのものに組み込まれる露出」を意識する点が大きな違いです。
ユーザーにとっては検索行動がより自然な会話型へと移行しているため、AIに情報を届けられるかどうかが今後の競争力を左右する重要な要素となります。
近年の検索体験は急速に変化しています。Googleは検索システムを大規模言語モデル(LLM)を中心に再設計し、従来の「リンク中心・キーワード中心」の仕組みから脱却して、文脈を理解した自然な対話形式の検索体験を実現しようとしています。
ユーザーもまた、検索窓に短いキーワードを入力するのではなく、「AIに直接質問する」という新しい行動様式を取り始めています。
LLMOが重要とされる背景
ChatGPTの登場を皮切りに、GeminiやPerplexityなどの生成AIツールが次々と普及し、私たちの情報収集行動は大きな転換期を迎えています。
これまでは検索エンジンにキーワードを入力し、検索結果から最適なページを選ぶのが当たり前でした。しかし現在では「AIに直接質問して答えを得る」というスタイルが急速に広がっています。
こうした流れの中で従来のSEO対策だけでは十分に成果を得られない場面が増え、AI時代に対応した新しい最適化手法としてLLMO(Large Language Model Optimization:大規模言語モデル最適化)が注目されるようになりました。
それでは、なぜ今LLMOがこれほど重要視されているのでしょうか。
ユーザー行動の変化とゼロクリック検索の増加
かつてはユーザーが疑問を解決するために検索エンジンを利用し、表示されたリンクをクリックして各サイトを訪れるのが一般的でした。
しかし現在では、検索結果の画面自体が大きく変わっています。
Googleが導入した「AI Overviews」では、検索結果ページの最上部に生成AIが要約した回答が表示されるようになり、ユーザーはリンクをクリックせずにその場で疑問を解決してしまうケースが増えています。
このような「ゼロクリック検索」の増加は、企業のオーガニック流入に直接的な影響を及ぼします。
Ahrefsの調査によると、AI Overviewが表示された検索結果では、上位ページの平均クリック率が34.5%も低下していることが報告されています。
つまり、従来のSEOで1位を取ったとしても、以前のようにアクセスを確保できるとは限らない状況になっているのです。
参照:AI Overviews Reduce Clicks by 34.5%
AI経由の新たな流入経路
一方で、AIの回答を通じた流入は確実に増加しています。Ahrefsの調査では、全Webサイトのうち63%にAI経由のトラフィックが存在しており、平均すると月間トラフィックの0.12%、訪問者の0.17%がAIを経由していることが確認されています。
数値だけを見ると小さく感じるかもしれませんが、AI利用が日常化するにつれ、この割合は今後さらに拡大することが予想されます。
実際に企業サイトにおいても、AI経由のアクセスが確認されており、中にはコンバージョン(資料請求や問い合わせ)にまでつながっている事例も出ています。
これはつまり、生成AIが従来の検索エンジンとは異なる「新たな流入経路」として機能し始めているということです。
企業がこの変化を無視すれば、将来的に顧客接点を失うリスクが高まるといえるでしょう。
参照:63%のサイトがAI経由のトラフィックを確認。3,000サイトの調査から見えた事実
ブランド認知と信頼構築への効果
「AIに引用されても直接的な流入やコンバージョンにはつながらないのでは?」と考える方もいるかもしれません。
しかし実際には、生成AIの回答に自社の情報やサービス名が繰り返し登場することで、ユーザーの記憶に定着しやすくなります。
その結果、時間をおいて指名検索やサービス利用へと発展する可能性が高まります。
さらに、指名検索が増えることでAIから「信頼できる情報源」として評価されやすくなり、回答内で引用される頻度がさらに上がるという好循環を生み出せます。
つまりLLMOは、単なる露出を増やすための施策ではなく、長期的にブランドの認知度と信頼を強化し、将来の顧客基盤を築くための重要な戦略なのです。
LLMOとSEOの違い
LLMO(Large Language Model Optimization:大規模言語モデル最適化)は生成AIに対する最適化であり、SEO(Search Engine Optimization:検索エンジン最適化)は検索エンジンに対する最適化です。
つまり、SEOは「検索結果に表示されること」を目指すのに対し、LLMOは「AIの回答に引用されること」を目標としています。
一見すると全く別の施策に思えますが、実際には重なり合う部分も多く存在します。
なぜなら、「AIに引用されやすいページ」には、すでに検索順位が高いページが多い傾向が見られるからです。
つまり、SEOで培ったノウハウはそのままLLMOにも活かすことができ、両者は補完関係にあるといえます。
| LLMO(大規模言語モデル最適化) | SEO(検索エンジン最適化) | |
|---|---|---|
| 対象 | 生成AI ChatGPT、Gemini、AI Overviewsなど | 検索エンジン Google、Yahoo、Bingなど |
| 目的 | AIの回答内での引用・参照・紹介 | 検索結果(SERPs)での上位表示 |
| 流入経路 | AIの回答文やページ紹介からのクリック | ・検索結果からのクリック |
| 成果指標 | 生成AIの回答での引用・表示回数 生成AIの回答からの流入数 | 検索結果における順位 自然検索からの流入数 |
SEOとLLMOは目的こそ違いますが、求められる要素には共通点が多くあります。
たとえば「構造化データ」や「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の強化」は、検索エンジンにとっても生成AIにとってもコンテンツを理解・評価する重要な指標です。
SEOでしっかりと整備された情報構造や高品質な記事は、生成AIにとっても理解しやすく、回答に引用されやすい形になるのです。
一方で、LLMOならではの特徴もあります。
生成AIは人間とは異なり、文脈や意味を「確率的」に解釈して回答を組み立てます。
そのため、人間にとって読みやすい文章だけでなく、「AIが理解しやすい文章構造」を意識する必要があります。
しかし、AIに最適化しすぎると今度は読者にとって不自然で読みにくい文章になってしまうリスクもあります。
したがって、SEOとLLMOの“いいとこ取り”をするようなバランス感覚が求められるのです。
SEOの現状とこれからのLLMOの戦略
生成AIの普及に伴い、一部では「SEOはもう不要になるのでは?」という声も聞かれるようになりました。
しかし結論から言えば、その答えは「No」です。
SEOとLLMOは対象や目的が異なるものの、どちらか一方で完結するのではなく、むしろ両輪として連携させることが、これからのWeb戦略において欠かせない要素です。
SEOは検索エンジンのアルゴリズムに沿ってコンテンツを最適化し、検索結果で上位表示されることで流入を獲得する施策です。
一方、LLMOはChatGPTやGeminiといった生成AIに自社情報を引用させ、ユーザーの質問に対するAIの回答の中で露出を確保することを狙いとしています。
SEOで整備した高品質な情報や明確なサイト構造は、AIにとっても「信頼できる情報源」として認識されやすくなり、回答への引用を後押しする点で両者は密接に関連しています。
また、現時点では、生成AI経由の流入はまだ全体のごく一部にとどまっています。
しかし、GoogleのAI Overviewsの導入により「ゼロクリック検索」が増加していること、さらに日常生活におけるAI検索の利用が急速に拡大していることを考えれば、今後はAI経由のトラフィックの比重が確実に大きくなると予測されます。
そのため、今後のマーケティングに求められるのはLLMOとSEOの「二軸の戦略」です。
すなわち、従来どおりSEOで検索流入をしっかり確保しつつ、同時にLLMOでAI検索における露出を高めるというアプローチです。
両者をバランスよく組み合わせることで、検索エンジンと生成AIという二つの主要チャネルをカバーでき、ブランドの認知拡大や信頼性の向上を持続的に実現できるでしょう。
LLMO対策の具体的な5つの方法
LLMO対策は「具体的に何をすればいいのか」と疑問に感じる方も多いと思います。
結論から言えば、その本質はSEOの延長線上にあり、SEOの基盤が不十分な状態では成果を出すことは難しいといえます。
Google検索セントラルでも「検索への表示に関する通常のガイダンスに従えば十分」と示されており、これはすなわち、適切なSEOの実施がAIからの引用を得るための前提条件になっているということです。
AI による概要と AI モードのための特別な最適化を行う必要はありませんが、次のようなこれまでの SEO の基本は引き続き重要となります。
引用元:AI 機能とウェブサイト(Google検索セントラル)
もちろん、近年話題に上がるLLMs.txtの導入や構造化データの最適化といったテクニカルな施策も、LLMOにおいて重要な役割を果たします。
しかし、それ以上に大切なのは「この分野ならこのサイトが信頼できる」とAIに認識されることです。
つまり、単に技術的対応に終始するのではなく、Web全体を通じて信頼性・専門性・権威性・存在感を築き上げることが不可欠なのです。
その延長線上でAIからの引用や参照が自然と生まれる、と考えると理解しやすいでしょう。
一次情報の公開
生成AIは、数値データや図表、調査結果といった「定量的な一次情報」を信頼できる情報源として引用する傾向があります。
そのため、自社で収集・分析したアンケート調査の結果やユーザー調査、アクセスログの解析データを表やグラフとともに公開することは、AIに引用される確率を高める有効な方法です。
一次情報とは「情報の出所が自社であること」を意味します。
他のメディアやサイトには存在せず、自社が初めて公開する独自の情報です。検索エンジンにおいても、オリジナリティの高いコンテンツは評価されやすく、SEOの観点からもプラスになります。
加えて、具体的な数値や根拠を伴う一次情報は、AIが「信頼性が高い情報」と認識しやすく、回答文に引用される可能性がさらに高まります。
特にAIに取り上げられやすい一次情報の例としては、以下が挙げられます。
・実験や検証を通じて得られたデータや知見
・専門家による市場分析レポートやインタビュー記事
・独自ツールやサービスを通じて蓄積された利用データや傾向
・社内施策の成果レポートやクライアント事例(インタビュー形式など)
・実際に体験した検証記事(例:生成AIの導入検証やSEO施策の効果検証)を写真やデータ付きで公開したもの
・数字ベースの成果指標(CV数、CPA、ROIなど)を公開し、読者に判断材料を提供するもの
一方で、自社発信ではなく他社の情報を引用する場合には注意が必要です。出典元を必ず明記し、可能であればリンクを設置することで、コンテンツ全体の透明性と信頼性を高められます。
また、引用先のサイト自体がE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を備えているかどうかも重要であり、引用元の選定も慎重に行うべきです。
単なる情報の寄せ集めではなく、独自のデータや具体的な事例を盛り込み、分析や検証を通じて深みのあるコンテンツを発信することが、SEOにもLLMOにも効果的に働きます。
AIに選ばれる情報源となるためには、オリジナリティと信頼性を兼ね備えた一次情報の発信が不可欠なのです。
HTML構造の最適化
LLMO(大規模言語モデル最適化)では、AIがコンテンツを正しく理解できるように、論理的で適切なHTML構造を設計することが非常に重要です。これはSEO対策と同様に基本的な取り組みですが、生成AIが正確に情報を解釈するためには、より丁寧な「セマンティック(意味的)なマークアップ」が求められます。特に現状では、多くのAIクローラーがJavaScriptのレンダリングに完全には対応していないため、HTMLベースで意味の通る構造を構築することが欠かせません。
HTMLタグの役割と適切な活用
それぞれのHTMLタグには固有の意味と役割があります。AIや検索エンジンはこれらの意味をもとにコンテンツを評価し、情報を整理していきます。
ページタイトルにはh1を1つだけ使用し、h2以降で階層構造を正しく示すことで、AIはコンテンツ全体のトピック構造を理解しやすくなります。
・段落タグ(p)
本文にはpタグを用いて文章のまとまりを明確に示します。
・リストタグ(ul・ol)
箇条書きや手順などを整理する際にはリストタグを活用することで、情報を体系的に表現できます。
・表タグ(table)
数値データや比較表を提示する際に効果的です。
・引用タグ(blockquote)
外部の情報やユーザーの声などを引用する際には適切に使用します。
これらの基本的なタグの活用によって、ページの情報が整理され、AIにとっても人間にとっても読みやすいコンテンツになります。
メタ情報と補助的なタグの活用
メタ情報と補助的なタグの活用は、HTML構造の最適化は本文だけに限りません。
ページ内容を端的に表現し、検索結果やAI要約で参照される可能性があります。
・メタディスクリプション(description)
簡潔で魅力的な要約を設定することで、AIがページの概要を把握しやすくなります。
・alt属性
画像に対して適切なaltテキストを設定することで、視覚的な情報もAIに正しく伝えることができます。
・構造化タグ(article・aside・navなど)
主要コンテンツや補足情報、ナビゲーションを明確に分けることで、コンテンツの意味がより明瞭になります。
HTML最適化がもたらす効果
適切なHTML構造はSEOの観点からも有効であり、検索エンジンのアルゴリズムがページを評価する際の重要な要素となります。
同時に、生成AIにとっても意味の通じる構造は「理解しやすいコンテンツ」として扱われ、引用・要約される可能性が高まります。
結果的に、SEOとLLMOの双方に良い影響をもたらし、検索エンジンからの流入増加とAI経由での露出拡大を同時に実現できるのです。
つまり、LLMOに取り組む際には特別な技術だけを意識するのではなく、HTMLの基本構造を正しく整えることが最も重要な第一歩 だといえます。
人間にもAIにも分かりやすい文章構成
生成AIに自社コンテンツを引用してもらうためには、「AIが理解しやすい文章や構成」を意識することが不可欠です。
人間は行間やニュアンスから意味を汲み取ることができますが、AIはあくまで単語の出現確率や文脈のつながりをもとに処理しています。
そのため、複雑な比喩や曖昧な表現よりも、明確で具体的な文章のほうが理解されやすく、引用の対象になりやすいのです。
特に効果的とされるのが以下の形式です。
ユーザーの疑問を想定し、「Q&A」の形で整理する方法。AIの回答パターンに近いため、そのまま引用されやすくなります。
・定義文形式
「〇〇とは、△△である」というように概念を明示する書き方。AIはこの形式を高精度で処理できるため、用語や新しい概念の説明に有効です。
・リストや表形式
箇条書き、番号付きリスト、表を使って手順やポイントを整理する方法。情報が構造化されるため、AIが引用・要約しやすくなります。
FAQ形式コンテンツの有効性
AIは「質問と回答のペア」を学習・処理するのが得意であるため、FAQ(よくある質問)形式のコンテンツは生成AIとの相性が非常に良いといえます。
わかりやすい一問一答形式にすることで、AIが情報を認識しやすくなり、回答文に引用される可能性も高まります。
さらにFAQは、AI対策として有効であるだけでなく、実際のユーザーにとっても疑問を解消できる便利なコンテンツです。
ユーザーの悩みや知りたい情報を事前に整理して提示しておくことで、利便性が向上し、顧客満足度の改善にもつながります。
質問内容を考える際には、自社のお問い合わせフォームに寄せられる相談や、営業現場でよく聞かれる質問を参考にするのがおすすめです。
これらは実際の顧客が抱える疑問なので、ニーズに直結した有効なコンテンツになります。
さらに、生成AIに「この事業領域でユーザーがよく抱く質問を教えて」と問いかけることで、新しい気づきを得られることもあります。
例えば、LLMOに関連したFAQの一例は以下の通りです。
A:生成AIが検索の入口として使われる機会が急増しており、ユーザーに自社情報を届けるには、AIに正確に引用・参照されることが欠かせないからです。
このようにFAQ形式を活用することで、ユーザーの疑問解消と同時にAIへの最適化を進めることができ、SEOとLLMOの両面で効果を発揮することが期待できます。
また、文章全体の構造を論理的に設計することも重要です。AIは複雑に入り組んだ文脈を苦手とするため、以下のようなパターンを活用すると効果的です。
ビジネス記事やハウツー記事で有効。
・起承転結(背景→展開→転換→まとめ)
ストーリー性が重視される記事で有効。
さらに、検索者がAIにどのような質問を投げかけるかを想定し、それを見出し(H2/H3)に設定し、本文で答える構成も効果的です。
AIの仕組みと親和性が高く、検索者の疑問に答える「引用候補」として扱われやすくなります。
文章の書き方にも工夫が必要です。一文を短めに区切り、段落ごとにトピックを整理することで、可読性も向上します。
これはユーザーにとって読みやすいだけでなく、AIにとっても学習しやすく、情報源として選ばれる可能性を高めます。
MITによると、大規模言語モデルは定義文や明示的な記述を好んで処理する傾向があることが示されており、マーケティング担当者は重要な概念やサービス説明に意図的にこのパターンを取り入れるべきだといえます。
つまり、「誰が読んでも理解できる論理的で明確な文章」は、人間にとって有益であると同時に、生成AIにとっても最適なコンテンツとなります。
SEOとLLMOの両方を意識するのであれば、まずはこの「AIに引用されやすい文章構造」を設計することが欠かせないのです。
E-E-A-Tの強化
生成AIに引用されるために最も重要な要素の一つが、「この分野ならこのサイトが信頼できる」とAIに認識されることです。
そのためには、Webサイト全体を通じて専門性や信頼性を高め、発信元としてのブランド力を確立する必要があります。
この考え方の基盤となるのが、Googleが提唱するE-E-A-T(Experience:経験、Expertise:専門性、Authoritativeness:権威性、Trustworthiness:信頼性)です。
E-E-A-TはもともとGoogle検索におけるコンテンツ品質評価の基準として重視されてきましたが、その思想は生成AIの評価プロセスにも共通しています。
AIは膨大な情報を処理する際に、単なる情報量や表現力ではなく、「誰が」「どのような経験や専門性に基づき」「どれほど信頼できる形で」情報を発信しているかを強く意識するようになってきています。
したがって、SEOと同様に、LLMOにおいてもE-E-A-Tを高めることが欠かせません。
E-E-A-Tを強化する具体的な施策
検索エンジンや生成AIから「信頼できる情報源」として選ばれるためには、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識した取り組みが欠かせません。
特にLLMOの観点では、ページ単位の最適化だけでなく、運営元全体としての信頼力やブランド価値が大きく影響します。
では、どのようにE-E-A-Tを高めていけばよいのでしょうか。実際に取り組むべき具体的な施策を整理してご紹介します。
実体験や顧客事例を盛り込むことで、リアルで具体的な知見を提供します。
ユーザーインタビュー、施策の実践記録、担当者の体験談などは、独自性が高くAIにとっても引用価値のある一次情報となります。
・Expertise(専門性)
特定のテーマに特化したコンテンツを体系的に発信し、専門的な立場を打ち出します。
著者のプロフィールや資格、経歴を明示することも効果的です。
オウンドメディア全体を一貫したテーマで設計することで、専門性がより強調されます。
・Authoritativeness(権威性)
外部メディアからの被リンクやサイテーション(他サイトやSNSでの言及)を獲得し、第三者からの評価を高めます。
また、専門家監修コメントや大学・研究機関のデータ引用なども権威性を裏付ける要素になります。
会社概要ページやトップページを充実させることも有効です。
・Trustworthiness(信頼性)
SSL化や利用規約、運営者情報の明記といった基本的な取り組みはもちろん、引用元を明確にし、ファクトチェックを徹底することで、ユーザーにもAIにも「安心できるサイト」であることを伝えられます。
さらに、定期的にコンテンツを更新し、情報の鮮度を保つことも信頼性を高めるポイントです。
E-E-A-TがSEOとLLMO双方に与える影響
E-E-A-Tを強化することは、SEOでの検索順位向上に直結するだけでなく、LLMOにおいてAIが「信頼できる情報源」と判断するための基盤にもなります。
事実、AIは第三者から評価されている情報源や、専門家によって裏付けられた情報を優先的に引用する傾向があります。
したがって、SEOとLLMOの両面で成果を出すためには、E-E-A-Tを高めることが不可欠です。
記事執筆においても、著者情報や専門的な背景を明記し、因果関係を論理的に示すことで、AIが文章を理解しやすくなります。
AWSのRAG技術解説でも指摘されているように、論理的に一貫したコンテンツは信頼性スコアが高く評価されやすく、生成AIの回答に引用される可能性も上がります。
つまり、E-E-A-Tの強化は単なるSEOのためだけでなく、AI時代において「この情報なら信頼できる」と認識されるための必須条件です。
SEOとLLMOの双方を意識した長期的な戦略の中核として、今から計画的に取り組むことが求められます。
サイテーションと被リンクによる権威性の強化
Webサイトの信頼性や権威性を高める上で欠かせないのが、サイテーション(言及)と被リンクです。
これらは従来のSEOでも重要な要素でしたが、生成AIが情報源の信頼性を評価する際にも大きな影響を与えると考えられます。
まず、質の高い被リンクは強力なシグナルです。
特に関連性の高い業界メディアや学術機関、行政・公的機関といった権威あるサイトから自然に得られるリンクは、自社サイトの評価を大きく底上げします。
検索エンジンにとってもAIにとっても、「他者から参照される=信頼できる情報」として扱われるからです。
一方で、サイテーション(言及)はリンクがなくても効果を持ちます。
ニュース記事や専門メディア、学術論文、SNS(X、noteなど)で、自社のブランド名やサービス名、所在地、電話番号などの固有情報が繰り返し登場することは、それ自体が知名度や信頼性を示すシグナルになります。
特に複数の信頼性の高いメディアから言及されている場合、AIから「広く認知されている情報源」として引用対象に選ばれる可能性が高まります。
こうした外部評価を得るためには、地道な広報活動や情報発信が不可欠です。具体的には以下のような取り組みが効果的です。
・専門家としてのイベント登壇やインタビュー対応
・SNSでの継続的な発信やユーザー参加型キャンペーン
・自社の代表者や有識者による対外的な情報発信
さらに、ブランド名や企業情報の表記を統一することも重要です。誤記や表記ゆれ(正式名称と略称の混在など)は評価を分散させる原因になりかねません。
特に実店舗を持つビジネスの場合、NAP情報(Name=名称、Address=住所、Phone number=電話番号)をWebサイト・SNS・外部ディレクトリで一貫させることが信頼性を高めるポイントになります。
外部からの評価を高めるには時間がかかりますが、着実に積み重ねることでSEOにもLLMOにも好影響を与え、結果的に「AIが信頼できる情報源」として自社が選ばれる可能性を大きく引き上げることができるのです。
サイトパフォーマンス最適化
Webサイトの表示速度やパフォーマンスは、SEOにおいてだけでなくLLMOにおいても非常に重要な要素です。
生成AIがWebページを参照する仕組みは検索エンジンのクローラーに似ており、ページの読み込みに時間がかかると、AIが十分に情報を取得できず、せっかく作成した高品質なコンテンツが正しく評価・引用されにくくなるリスクがあります。
Googleも検索順位を決定する要因のひとつとして「コアウェブバイタル(Core Web Vitals)」を導入しており、表示速度や操作性などの指標を重視しています。
これはユーザー体験の向上だけでなく、クローラーが効率的に情報を処理できる環境を整えるためでもあり、その考え方はLLMOにも直結します。
つまり、サイトの表示速度や安定性が高いほど、AIにとっても内容を読み取りやすくなり、引用対象として認識されやすくなるのです。
表示速度を改善するメリットは多岐にわたります。ユーザー側では、読み込みが早いほど離脱率が低下し、快適にサイトを利用できるため、滞在時間やコンバージョン率の向上が期待できます。
一方、AIや検索エンジン側では、ページをスムーズにクロール・処理できるため、サイト全体の評価向上につながります。
パフォーマンス最適化に取り組む際には、Googleが提供する「PageSpeed Insights」などのツールを活用し、現状のスコアを確認して改善していくのがおすすめです。
具体的には、画像の圧縮やキャッシュの活用、不要なスクリプトの削除、モバイル対応の強化などが有効な手段となります。
結局のところ、表示速度の最適化は「人にもAIにも優しいサイトづくり」の基本です。
SEOとLLMOの両面で成果を高めるために、日常的にサイトパフォーマンスをチェックし、継続的に改善していく姿勢が求められます。
SEO対策の重要性
AIにコンテンツを引用してもらうためには、「検索順位が高いページ」であることが大きなアドバンテージになります。
なぜなら、生成AIは検索エンジンで評価されたページを“信頼できる情報源”として参照する傾向が強く、すでに検索上位にあるコンテンツはAIにとっても優先的に回答へ組み込みやすいからです。
検索順位の高いページは、信頼性や網羅性が高く(E-E-A-Tが確立されている)、ユーザーの検索意図に的確に合致し、実際に多くの人に読まれているページです。
つまり、人間にとって価値があると認められたページであり、AIも同じ視点から「利用価値が高い」と判断しているのです。
この点からも、LLMOにおいても基本的なSEO対策は欠かせません。構造化データの整備やE-E-A-Tの強化といった取り組みは、従来のSEOと重なる部分が多く、結果的にAIからの引用チャンスを増やすことにつながります。検索エンジンに評価されることで露出機会が増えれば、その分だけ生成AIにも情報を提供する機会が増える、という構造になっているのです。したがって、LLMOはSEOと完全に別物ではなく、「SEOの進化形」として捉えることができます。
さらに、AI検索時代には「SEOとLLMOを統合したハイブリッド戦略」がますます重要になります。
従来の検索エンジンはリンク型の情報表示を基本としてきましたが、生成AIは要約や引用型の表示を得意としています。両者は対立するのではなく、ユーザーの情報接点を多様化させる補完関係にあるのです。
Google Developersの報告によると、AI機能を組み込んだ検索環境ではユーザーがより複雑な質問を行うようになり、検索体験そのものへの満足度も向上しているとされています。
Google がこれまでおすすめしてきた基本的な指針は、新しいエクスペリエンスにも当てはまります。それは訪問者を第一に考え、満足度の高い独自のコンテンツを提供することです。
引用元:Google 検索の Google AI エクスペリエンスでコンテンツのパフォーマンスを高めるための主な方法
従来のSEOとLLMOは全く別物というよりも、むしろ地続きの関係にあります。
SEOによって整えられた高品質な情報構造や専門的なコンテンツは、検索エンジンに評価されると同時に、生成AIにとっても「信頼できる情報源」として扱われやすくなります。
事実、検索順位が高いページはAIにも引用されやすい傾向が確認されており、この点からもSEOとLLMOは相互に補完し合う存在だといえます。
ただし注意すべきは、AIは人間とは異なるロジックで文章を理解・生成するため、LLMOではAIが解釈しやすい文章構造や情報提示を意識する必要がある点です。
とはいえ、AIに合わせすぎると今度は人間にとって読みづらい文章になってしまうリスクもあるため、SEOとLLMOの両立を意識した「バランス感覚」が求められます。
最終的に、マーケティング担当者は「検索順位」と「AIからの引用率」の両方を検索エンジンマーケティングの目標として設定し、SEOとLLMOを組み合わせた最適化を継続的に行う必要があります。
この双方向アプローチにより、検索エンジンとAI検索の双方に強いプレゼンスを確保でき、技術の進化に柔軟に対応しながら長期的なブランド露出を実現することができるでしょう。
このように、SEOとLLMOはどちらか一方に偏るのではなく、両者を組み合わせることで最大の効果を発揮します。
これからのWeb戦略においては、SEOで検索流入を安定的に確保しながら、同時にLLMOで生成AI経由の露出を高めるという二軸の取り組みが必須となるでしょう。
まとめ:LLMOはSEOの延長であり、次世代の必須戦略
生成AIの普及により、ユーザーの情報収集行動は大きく変化しています。従来の「検索エンジンにキーワードを入力して探す」スタイルから、「ChatGPTやGeminiに直接問いかける」スタイルへと移行しつつあり、今後は検索の役割が「探す」から「答える」へシフトしていくと予測されます。こうした変化の中で、AIに正しく引用されるための最適化=LLMO(大規模言語モデル最適化)が、Webマーケティングにおける重要な戦略のひとつとなっています。
LLMOは全く新しい概念というよりも、既存のSEO施策を土台にした延長線上の取り組みです。これまでと同様に「ユーザーに価値ある情報を提供し、信頼を得る」という基本姿勢は変わりません。その上で、AIに選ばれるための工夫として独自の一次情報の発信やエンティティ情報の整理が鍵になります。現時点で本格的に取り組む企業はまだ少なく、先行者メリットを得るためにも早めの着手が望ましいでしょう。
一方で、LLMOには「変化が激しい」「効果測定が難しい」といった特徴もあります。そのため、焦って短期的な成果を求めるのではなく、SEOと並行して冷静に中長期的に取り組むことが重要です。SEOでの基盤整備(サイト速度、構造化データ、E-E-A-Tの強化など)は、AIにとっても信頼できる情報源として評価されるため、両者を連携させることで安定した成果が期待できます。
さらに、LLMOは単なる技術的施策にとどまらず、ブランディング全体の強化とも直結します。AIに「この分野ならこの企業」と認識されるには、SEOに加えて広報・PR、SNSでの発信、セミナーや外部メディア掲載といった多角的な取り組みが欠かせません。AI経由の流入増加だけでなく、「ブランドとして指名される未来」をつくることこそ、LLMOの本質的な狙いです。
改めてまとめると、LLMO対策において意識すべきポイントは以下の通りです。
SEOはLLMOの土台であり、両者の連携が成果を最大化する。
・高品質コンテンツとE-E-A-T
ユーザーにもAIにも信頼される情報提供を心がける。
・テクニカル施策
HTML構造、サイト速度改善、UIUX向上などを実現する。
・ブランディング活動
外部からの評価や認知を広げる取り組みを継続する。
・中長期的視点
短期の効果に一喜一憂せず、分析・改善を重ねる。
LLMOは単なる小手先の「テクニック」ではなく、企業やメディアが持つべき根本的な「姿勢」だと言えます。
検索環境は生成AIの登場によってこれまで以上に変化のスピードが速まり、従来のSEOだけでは対応しきれない局面が増えてきました。
そのような中で重要なのは、一時的な流入増加を狙うことではなく、ユーザーにもAIにも「この情報は信頼できる」と認めてもらえる誠実な情報提供を継続することです。
具体的には、ユーザーの課題を的確に解決する高品質なコンテンツを発信し続けること、そしてAIが正しく理解・引用できるような構造や形式を整備することが求められます。
こうした積み重ねによって、検索エンジンや生成AIの仕組みが変化しても揺るがない「ブランドとしての信頼」が育まれます。
つまり、LLMOの本質はテクニカルなノウハウの積み上げではなく、誠実に価値を提供し続ける姿勢そのものです。
この姿勢を軸に据えることこそが、これからのWebマーケティングを長期的に成功へと導く最大の鍵になるのです。